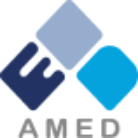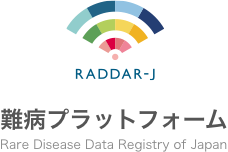| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
| 研究課題名 | SaCas9/AAV改変と数理学的な臨床試験のデザインによる網膜ゲノム編集遺伝子治療の統合的開発 | |
| 研究代表者名 | 西口康二 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 国立大学法人東海国立大学機構 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | 網膜色素変性 | |
| 研究のフェーズ | シーズ探索研究 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | あり | |
| 研究概要 | 網膜色素変性(RP)は、有効な治療法がない失明原因第2位の遺伝性網膜変性である。現在、アデノ随伴ウィルス(AAV)を使って病因遺伝子の正常コピーを補填する遺伝子治療の開発が主流である。しかし、ベクター容量の制約のため、大きな遺伝子を病因とする大多数の日本人RPに応用できない。この問題に対して、申請者らは、ゲノム局所を治療対象とすることで、遺伝子の大きさに関わらず治療できるゲノム編集遺伝子治療の開発を行ってきた。 R3年度からは、企業と連携し、日本人RPの12%が保有するEYS-S1653Kfs(1塩基挿入変異)に対するゲノム編集治療の開発に着手した。我々は、変異特異的なゲノム切断により挿入変異が高頻度で一塩基脱落しズレたフレームが元に戻る治療戦略(リフレームゲノム編集)を見出し、関連特許を共同出願した。R4-R5年度はAMEDの支援を受けており、計画を前倒ししてマウスからサルにモデルを変更しin vivoゲノム編集成功率13.9%を達成するなど、主要なマイルストンは順調にクリアしている。並行して、RPに対する世界最大級の遺伝子解析研究を実施し、EYSを病因とする患者(EYS患者)を過去最多数同定した。 しかし最近になって、RP類縁疾患に対する世界初のAAVゲノム編集遺伝子治療の治験で、薬の効果が想定よりも小さかったことと治験の中止が発表された。この結果を受けて、この治療薬の開発研究を参考に設定した、前臨床試験に進む条件としたゲノム編集成功率の目標値を現在の10%から20%に大幅に引き上げることにした。具体的には、ゲノム編集効率の劇的な改善が報告された、改変の対象領域内の各アミノ酸に対して全19種類のアミノ酸変異体を網羅的にスクリーニングを行うDeep Mutational Scanning(DMS)を用いたCasの最適化とAAV-YF変異体の検討などAAVカプシドの改良を行う。さらに、世界最大のEYS患者レジストリと先端的な数理学的アプローチを組み合わせることで、治療効果が効率的に検出可能な病期と臨床バイオマーカーを同定し、その有用性を次の前臨床試験で前向き検証するなど、基礎研究と臨床研究の両輪で医師主導治験成功の確率を上げることを目指す。 | |
| レジストリ情報 | ||
| レジストリ名 | ||
| 対象疾患/指定難病告示番号 | ||
| 目標症例数 | 300 例 | |
| 登録済み症例数 | 100 例 | |
| 研究実施期間 | ||
| 関連学会との連携の有無 | なし | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | あり | |
| レジストリの目的 | 患者数や患者分布の把握;治験またはその他の介入研究へのリクルート;遺伝子解析研究 | |
| レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
| 臨床情報の調査項目 |
| |
| 調査項目 | ||
| 第三者機関からの二次利用申請可否 | 不可 | |
| レジストリの企業利用について | 企業が利用することについては、患者の同意を取得していない | |
| 二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
| レジストリURL | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| 生体試料の種類 | 血漿・血清;DNA | |
| 生体試料の登録例数 | 500 | |
| 外部からの使用申請の受け入れ可否 | 不可 | |
| 外部からの使用申請への対応 | ||
| 担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。