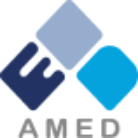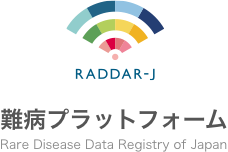| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
| 研究課題名 | (研究課題9) | |
| 研究代表者名 | 前田大地 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 金沢大学 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | 間質性膀胱炎(ハンナ型) | |
| 研究のフェーズ | 病態解明研究 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| 研究概要 | 【背景】間質性膀胱炎・膀胱痛症候群(IC/BPS)は膀胱・下腹部痛や頻尿、尿意切迫などの症状を来す原因不明の慢性疾患で、間質性膀胱炎ハンナ型(HIC)と膀胱痛症候群(BPS)に分類される。我々はIC/BPSの病理学的研究を行ってきた過程で、HICの本態が膀胱全体に及ぶB細胞、特に形質細胞を主体とする炎症性疾患であるのに対して、BPSは組織学的に炎症所見の乏しい非炎症性疾患であることを明らかにした。また全ゲノム関連解析(GWAS)により、HICの発症リスクには複数のHLA遺伝子多型が関与していることを突き止め、その免疫疾患としての位置づけを確固たるものとしてきた。HICでは特に患者のQOL障害が著しく、2015年には指定難病となっている。現在、厚生労働省難治性疾患政策研究班による患者レジストリ登録が進められており、申請者はその班員として活動している。このように、疾患概念の整理、臨床像の把握が大幅に進んだものの、免疫疾患としてのHICの成因は現状では未解明のままである。また、分子細胞学的知見に基づく治療標的探索はほとんどなされていない。 【目的】我々はIC/BPS症例の膀胱組織検体を対象として定量的な病理学的検討を行った結果、世界に先駆けてHICにおいて高頻度にB細胞のクローン性拡大が起きていることを証明した。その詳細を検討すべく、次世代シーケンサーを活用したB細胞抗原受容体レパトア解析を実施し、HIC患者の膀胱におけるB細胞クローンの時空間的広がりに関する初期的データを得るに至っている。HICがB細胞の異常によって惹起される疾患である蓋然性が高いことから、本研究では最新のゲノム解析技術を導入しつつ、さらに踏み込んで、膀胱全摘検体を含む多数例のHIC検体を用いたB細胞クローンの動態解析を実施する。その目的は以下の3点に集約される。 ①HICにおいてB細胞のクローン性拡大を誘導する因子を同定した上で、それらの治療標的、診断マーカーとしての意義を探求する。 ②症例を越えた共通B細胞クローンを探索し、HICの原因抗原を特定する。 ③膀胱組織におけるB細胞クローンの位置情報をふまえた臨床病理学的検討を行い、HICの重症度を反映した病理学的グレーディングを確立する。 【方法】 ① B細胞のクローン性拡大を誘導する因子の同定 HICの生検検体(約30例)、膀胱全摘検体の複数箇所から採取したマルチリージョン解析用検体(約20個)を対象として、B細胞レパトア解析を行い、各検体におけるB細胞クローンの組成、ドミナントクローンの有無を明らかにする。新規症例に関してはシングルセルレパトア解析を活用して、個細胞レベルでのデータを得る。レパトア解析と並行して各検体のRNA-seqを行い、B細胞クローンの偏り(D50 index)とトランスクリプトームの連関を検討することで、B細胞クローンの拡大に寄与する因子を同定し、分子標的治療の対象となりうるものを絞り込む。そして、各因子の血清・尿中マーカーとしての意義を検討する。 ② HICの原因抗原の特定 B細胞レパトア解析において検出されたドミナントクローン、および症例を越えて存在した共通クローンのCDR3領域の配列をもとにリコンビナント抗体(約20種類)を作成する。これらの抗体を用いてタンパク質アレイ解析を施行し、各抗体が結合するタンパク質を同定する。複数の抗体が結合したものを原因抗原の候補とみなし、そのヒト膀胱組織における局在を検証した上で、その病的意義を探求する。 ③ 病理学的グレーディングの確立 病理組織検体におけるドミナントB細胞クローンの局在パターンをRNA-ISH法で認識し、空間的遺伝子発現解析によって得られるその他の炎症細胞や上皮細胞の局在データと統合することで、HICの重症度と相関するパラメーターを取得し、それをもとに新規の病理学的グレーディングを構築する。 | |
| レジストリ情報 | ||
| なし | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| 生体試料の種類 | 血漿・血清;DNA;RNA;組織;尿 | |
| 生体試料の登録例数 | 300 | |
| 外部からの使用申請の受け入れ可否 | 不可 | |
| 外部からの使用申請への対応 | ||
| 担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。