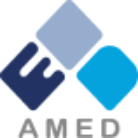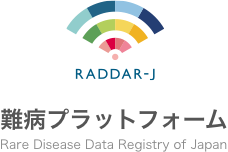| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
| 研究課題名 | 骨再生制御材料を用いた頭蓋骨縫合早期癒合症の低侵襲治療法確立 | |
| 研究代表者名 | 玉田一敬 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター 形成外科 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | 頭蓋骨縫合早期癒合症 | |
| 研究のフェーズ | 非臨床試験 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| 研究概要 | 本研究において開発するのは2つの接着性パテ状骨補填材で、骨欠損部位には骨再生の促進材料(リン酸化プルラン凍結乾燥品、2%塩化カルシウム水溶液、β-TCP粉末を用時調整して得られた混合物)、早期癒合の切除部位には再癒合防止のため骨再生の遅延材料(リン酸化プルラン凍結乾燥品、ゲル化剤(2%塩化カルシウム水溶液または2%ポリリジン水溶液)、α-TCP粉末を用時調整して得られた混合物を用いる。これら2つの接着性パテ状骨補填材については、令和4~6年度医療機器等研究成果展開事業にて基本組成は決定している。 本研究開発では、まず頭蓋骨縫合早期癒合症の骨補填材開発に適した動物実験モデルを確立し、これらの骨再生制御材料の組成を最適化する。頭蓋骨縫合早期癒合症の治療用材料として骨再生の促進材料と遅延材料は実用化された実績がなく、現状では開発の指標と成り得る最適な動物モデルもない。そこで本研究では、動物モデルの開発から着手する。 さらに、骨再生の促進材料と遅延材料の組成を最適化した後、生物学的安全性試験(GLP)を実施し、治験のプロトコール作成を本研究開発(医療機器ステップ1)の期間中に完了することで、スムーズに医師主導治験(医療機器ステップ2)に移行する。 本研究において想定している骨再生促進材料と骨再生遅延材料を用いることで、難病指定されているクルーゾン症候群(告知番号:181)、アペール症候群(告知番号:182)、ファイファー症候群(告知番号:183)、アントレ―・ビクスラー症候群(告知番号:184)や単独の症状として生じる頭蓋骨縫合早期癒合症における早期癒合の切除部位の再癒合防止と骨欠損部の骨再生に資する有効な医療機器と成り得る。 また、最も難症例と見做せられる頭蓋骨縫合早期癒合症にて有効性を明らかにすることができれば、骨再生促進材料については脳神経外科領域、整形外科領域、形成外科領域における様々な骨欠損や、歯科口腔外科疾患(歯周病やインプラント周囲炎による歯槽骨・顎堤の欠損、悪性腫瘍や良性腫瘍、嚢胞等を切除した部位に生じる骨欠損)への適用拡大が期待できる。さらに、骨再生遅延材料についても整形外科領域における先天性橈尺骨癒合症や、形成外科・口腔外科領域の顎関節強直症への適用拡大が考えられる。 | |
| レジストリ情報 | ||
| なし | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| なし | ||
| 担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。