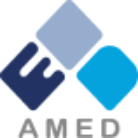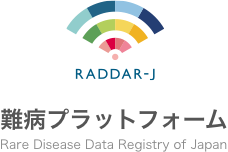| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患政策研究事業 | |
| 研究課題名 | 難治性血管炎の医療水準・患者QOL向上に資する研究 | |
| 研究代表者名 | 田村直人 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 順天堂大学医学部 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | 原発性血管炎 | |
| 研究のフェーズ | 病態解明研究;疫学研究;診断基準、分類基準の改訂、ガイドライン作成、啓発・普及 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | あり | |
| 研究概要 | 【目的】難治性血管炎の診療、研究開発における中心的組織として、指定難病および小児慢性疾患の難治性血管炎疾患を対象とし、難病・小児慢性特定疾病対策の推進を図り、難治性血管炎疾患の医療水準や患者のQOL向上に貢献する。1)血管炎に関する啓発・知識の普及、2)診療ガイドライン(CPG)改訂、3)血管炎診療、CPG、診断基準、重症度分類の検証、研究、4)AMED申請研究課題の連携推進、5)国際的活動の推進、等を行う。【方法】研究班全体としてJPVAS血管炎前向きコホート研究を推進するとともに、5つの各分科会で研究課題の継続、新規研究を実施した。【結果】これまでの主な活動として、領域横断分科会では、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の診療実態に関するアンケート調査を実施、大型血管炎診療実態アンケート解析結果を論文化した。研究班ホームページを改訂、英語版を追加した。複数学会で合同シンポジウムを行い、血管炎診療の最新知識を共有した。臨床病理分科会では、血管炎病理診断コンサルテーションを継続し、適切な血管炎病理診断のための「血管炎病理診断のために有用な染色プロトコル集」を作成中である。大型血管炎臨床分科会では、診療ガイドライン改訂中であり、来年度公開予定である。後ろ向きコホート研究を用いた巨細胞性動脈炎の診断基準案を検討中である。後ろ向きコホート研究の解析結果から2022ACR/EULAR分類基準の巨細胞性動脈炎分類能に関する論文、高安動脈炎の治療経過に関する論文を投稿した。バージャー病、高安動脈炎の個人調査票解析結果をそれぞれ論文化した。AMED研究班と連携し高安動脈炎合併症バイオマーカーに関する多施設研究を開始した。中・小型血管炎臨床分科会では、2022ACR/EULAR分類基準の日本人患者の分類能を論文化した。JPVAS前向きコホート(RADDER-J)の中間解析を行っている。好酸球性多発血管炎性肉芽腫症ガイドラインを改訂中である。結節性多発動脈炎の全国疫学調査の解析を行った。C5a受容体阻害薬投与患者の前向きコホート研究を開始した。国際臨床研究分科会では、アジア環太平洋リウマチ学会(APLAR)と共同の高安動脈炎国際シンポジウムを開催したほか、海外演者による講演会を行った。国際会議に参加して意見交換を行い、複数の国際共同研究を促進した。【考案】これらの研究を発展させ、さらなる成果を得ることにより、難治性血管炎の医療水準や患者のQOL向上に貢献が可能であると考えられる。 | |
| レジストリ情報 | ||
| レジストリ名 | 顕微鏡的多発血管炎と多発血管炎性肉芽腫症に対するアバコパンの有効性と安全性を検証する多施設共同前向きレジストリ研究 | |
| 対象疾患/指定難病告示番号 | 顕微鏡的多発血管炎/43、多発血管炎性肉芽腫症/44 | |
| 目標症例数 | 400 例 | |
| 登録済み症例数 | 25 例 | |
| 研究実施期間 | 2024年7月~2026年6月 | |
| 関連学会との連携の有無 | なし | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| レジストリの目的 | 日本人における実臨床での安全性、有効性の検討 | |
| レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
| 臨床情報の調査項目 |
| |
| 調査項目 | ||
| 第三者機関からの二次利用申請可否 | 不可 | |
| レジストリの企業利用について | 企業が利用することについては、患者の同意を取得していない | |
| 二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
| レジストリURL | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| 生体試料の種類 | 血漿・血清 | |
| 生体試料の登録例数 | 25 | |
| 外部からの使用申請の受け入れ可否 | 不可 | |
| 外部からの使用申請への対応 | ||
| 担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。