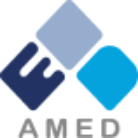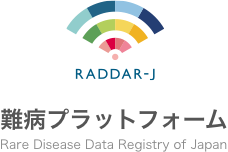| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
| 研究課題名 | 超希少難病である特発性胸膜肺実質線維弾性症(iPPFE)における疾患レジストリの構築と治療最適化のためのTreatable traitsの究明 | |
| 研究代表者名 | 宮崎泰成 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 東京科学大学 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | 特発性間質性肺炎 | |
| 研究のフェーズ | エビデンス創出研究 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| 研究概要 | 特発性胸膜肺実質線維弾性症(Idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis: iPPFE)は、特発性間質性肺炎:難病85(Idiopathic interstitial pneumonias: IIPs)の国際分類の一つである。IIPs の罹患数は国内推定1 万5 千人、iPPFE はその5〜6%とされ、超希少疾患のため正確な統計は存在しないが、罹患数は国内推定約900~1000 人未満となる。扁平胸郭や羸痩といった身体所見を有することが特徴であり、体重減少が進行し始めた後は気胸や縦隔気腫をともない呼吸困難が進行する。これにより著明なQOL低下と予後の悪化を来すが、現在のところ肺移植以外に有効な治療法のない超希少難治性疾患である。ガイドラインにも治療についての推奨がなく、一般内科医に知名度が低い希少疾患であるために早期発見されていない症例が多い。現在予後を改善するエビデンスのある治療は肺移植のみであるが、肺移植も待期期間の長さから、急速進行例では実施に至らない症例が多いことが問題となっており、早期から肺移植登録すべき症例を発見することは重要な課題である。薬物治療としては他の間質性肺炎で用いられている抗線維化薬が使用されているが、コラーゲン増生を抑制する薬剤であるため効果がある患者は限られる。どのような患者であれば抗線維化薬を使用すべきか検討が必要である。本研究では厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業 びまん性肺疾患に関する調査研究班(班長須田隆文、PPFE 部会長宮崎泰成)の協力を得て患者集積を行い、本邦最大のレジストリを作成し、①iPPFE レジストリ構築による臨床像の解明すること、②肺移植、抗線維化薬の治療適応となる群を発見すること(treatable traits の解明)、③iPPFE のバイオバンク創設による遺伝子および発現タンパク病態解明からの新規治療の探索を目的としている。これらの結果からどのような患者に早期に肺移植登録をすべきであるか、どのような患者に抗線維化薬を使用すべきであるかを明らかにし、間質性肺炎診療の次期ガイドライン改訂に記載するエビデンスとする。本研究の最終的な目標は超希少疾患のため解析が不十分であったiPPFE の病態解明と、それを通して治療法を開発し、予後改善を図ることにある。得られた情報をガイドラインの次期改定に掲載し、一般呼吸器科医および患者会に発信することで、希少疾患であるために治療を得られない患者を減らしたい。 | |
| レジストリ情報 | ||
| レジストリ名 | Treatable PPFE | |
| 対象疾患/指定難病告示番号 | IIPs/85 | |
| 目標症例数 | 250 例 | |
| 登録済み症例数 | 215 例 | |
| 研究実施期間 | 2024年4月〜2027年3月 | |
| 関連学会との連携の有無 | あり | |
| 学会名 | 日本呼吸器学会 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| レジストリの目的 | 自然歴調査;患者数や患者分布の把握;疫学研究;バイオマーカーの探索;遺伝子解析研究 | |
| レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
| 臨床情報の調査項目 |
| |
| 調査項目 | ||
| 第三者機関からの二次利用申請可否 | 可 | |
| レジストリの企業利用について | 企業が利用することについては、患者の同意を取得していない | |
| 二次利用申請を受けた場合の対応方法 | 運営委員会で協議後、倫理委員会の承認を得て提供する。 | |
| レジストリURL | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| 生体試料の種類 | 血漿・血清;DNA | |
| 生体試料の登録例数 | 215 | |
| 外部からの使用申請の受け入れ可否 | 本研究終了後可能とします | |
| 外部からの使用申請への対応 | 委員会の承認 研究プロトコール 倫理委員会での承認が必要 | |
| 担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。