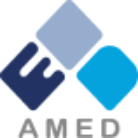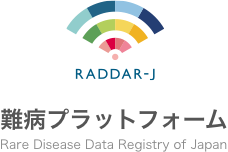| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患政策研究事業 | |
| 研究課題名 | 自己免疫性出血症診療の「均てん化」のための実態調査と「総合的」診療指針の作成 | |
| 研究代表者名 | 橋口照人 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症(指定難病 288) | |
| 研究のフェーズ | 病態解明研究;バイオマーカー・診断薬の開発研究 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | あり | |
| 研究概要 | 本研究は、自己免疫性後天性凝固因子欠乏症(指定難病 288)(以下、AiCFD)の診療の均てん化を目標として現顧問の山形大学名誉教授 一瀬白帝により 2009 年に厚労科研による研究班が立上げられて以来、全国からの症例相談を継続し、実態の解明、診断基準、重症度分類、診療ガイドライン等を作成、確立、改定してきた。次の 3 年間においてこれまでの活動を継続・発展させ、症例レジストリや検体バイオレポジトリを加速化させ、研究協力者(企業)に本研究事業に参画して頂き、2014-2016 年度 AMED 難治性疾患実用化研究事業(一瀬前研究班代表ら)「後天性凝固異常症の P.O.C.テストによる迅速診断システムの開発」で作成した検査方法を活用・改良して AiCFD 確定診断に必須な各抗凝固因子自己抗体検出検査を簡便化し、診断手法を研究室での解析から臨床医の鑑別診断のための検査として一般化させることを目的とする。本申請により現在の活動を継続するとともに診断手法を研究室での解析から臨床医の診断のための検査として一般化することにより AiCFD を簡易かつ迅速に確定診断することが可能となり、もって AiCFD 診療を格段に改善して国内のみならず世界の AiCFD 医療の水準を向上が期待できる。また AiCFD 疑い症例に対して AiCFD を明確に否定することも不必要な免疫抑制療法を回避できることから症例の予後に貢献することも期待できる。AiCFD の本邦における実態把握、エビデンスに基づいた診療ガイド等の確立、普及及び改定等の継続による AiCFD 全体の診療水準の継続的向上・最適化が加速される。また、症例を 直接診察する非専門医に本症について周知するので、診断、治療の「均てん化」が促進される。 <長期的な効果> 本研究は、2009 年より一瀬前研究班代表らにより AiF13D の実態調査として開始されたが、当初は除外されていた AiF8D、AiVWFD、AiF5D、 AiF10D 等も包含して自己免疫性出血症全体を対象とする網羅的な事業へ発展してきた。AiCFD には共通の免疫機序が働いている可能性が高く、AiCFD の一元的な疾患像の理解と、有用性が証明された検査、診断、治療方法の情報共有により AiCFD への対策が効率良く発展するとともに医療経済への貢献も期待できる。 | |
| レジストリ情報 | ||
| レジストリ名 | 出血症診療の実態調査 | |
| 対象疾患/指定難病告示番号 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症/288 | |
| 目標症例数 | 100 例 | |
| 登録済み症例数 | 17 例 | |
| 研究実施期間 | 2021年4月~2027年3月 | |
| 関連学会との連携の有無 | あり | |
| 学会名 | 日本血栓止血学会 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | あり | |
| レジストリの目的 | 自然歴調査;患者数や患者分布の把握;疫学研究;試料採取;主治医への情報提供 | |
| レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
| 臨床情報の調査項目 |
| |
| 調査項目 | ||
| 第三者機関からの二次利用申請可否 | 不可 | |
| レジストリの企業利用について | 企業が利用することについては、患者の同意を取得していない | |
| 二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
| レジストリURL | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| 生体試料の種類 | 血漿・血清 | |
| 生体試料の登録例数 | 20 | |
| 外部からの使用申請の受け入れ可否 | 不可 | |
| 外部からの使用申請への対応 | ||
| 担当者連絡先 | ||
| 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 血管代謝病態解析学分野 橋口照人 k1581347●kadai.jp | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。