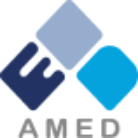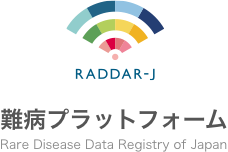| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
| 研究課題名 | 急性網膜壊死の診療ガイドライン作成に向けたレジストリの構築とエビデンスの創出 | |
| 研究代表者名 | 臼井嘉彦 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 東京医科大学 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | 急性網膜壊死 | |
| 研究のフェーズ | エビデンス創出研究 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| 研究概要 | 本研究では、まず初年度には、日本眼炎症学会が主導するレジストリを構築し本疾患に関する臨床情報、画像データ、診断方法やウイルス解析方法、硝子体手術の適応や時期について収集し、レジストリ(J-ARN)に集積する。眼炎症学会から参加希望施設を募り、これらの施設での研究倫理審査やレジストリに関するシステム構築を支援していく。レジストリは前向きレジストリと後ろ向きレジストリに分け、学術的見地からガイドライン作成に向けたエビデンスを確立し、有効な治療法をガイドラインとして提唱することを目的とする。集積された患者情報の解析により、様々な重要な臨床課題(CQ)の解決に資するリアルワールドエビデンスを創出する。CQについては、日本眼炎症学会内の急性網膜壊死ワーキンググループのぶどう膜炎専門医メンバーで協議を行い、ガイドライン作成に必要と思われる以下の項目を設定した。 1. 急性網膜壊死の早期診断に有用な特徴は何か? 2. 抗ウイルス薬の投与量・投与期間はどれくらい必要か? 3. 抗ウイルス薬にどのくらいのステロイドを併用した方がよいか? 4. 抗ウイルス薬はアシクロビル点滴とバラシクロビルなどの内服治療のどちらの効果が高いか? 5. どのような症例に予防的硝子体手術が必要か? 6. 手術方法(シリコンオイルの使用、輪状締結の併用など)による経過の違いはあるか? 7. ヘルペスウイルスの種類やコピー量により急性網膜壊死の視力予後は異なるか? 8. 急性網膜壊死の視機能に影響する因子は何か? 次年度よりさらに臨床情報と画像情報を統合し、人工知能解析を行う。莫大な症例数が必要となるディープラーニング(深層学習)のような人工知能による学習ではなく、限られた症例数でも学習可能なランダムフォレストと線形サポートベクターマシン、ラジアル基底関数を用いたサポートベクターマシン、決定木、単純ベイズ分類器の5種類の機械学習を臨床データと画像情報を統合して解析を行い、多次元情報による発症、診断や治療効果判定および視力予後判定の確立に向けた数理モデルの開発を行う。前年度までの情報を収集・解析を継続し、最終的に日本眼科学会が主導するナショナルデータベース Japan Ocular Imaging Registry (JOI registry)との連携も行っていく。 | |
| レジストリ情報 | ||
| レジストリ名 | J-ARN | |
| 対象疾患/指定難病告示番号 | 急性網膜壊死 | |
| 目標症例数 | 500 例 | |
| 登録済み症例数 | 0 例 | |
| 研究実施期間 | 2024年4月~2027年3月 | |
| 関連学会との連携の有無 | あり | |
| 学会名 | 日本眼炎症学会 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| レジストリの目的 | 自然歴調査;患者数や患者分布の把握;疫学研究;試料採取;バイオマーカーの探索 | |
| レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
| 臨床情報の調査項目 |
| |
| 調査項目 | ||
| 第三者機関からの二次利用申請可否 | 不可 | |
| レジストリの企業利用について | 企業が利用することについては、患者の同意を取得していない | |
| 二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
| レジストリURL | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| 生体試料の種類 | 血漿・血清;眼内液 | |
| 生体試料の登録例数 | 500 | |
| 外部からの使用申請の受け入れ可否 | 不可 | |
| 外部からの使用申請への対応 | ||
| 担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。