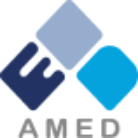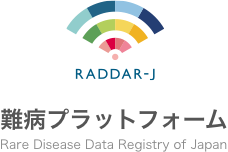| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
| 研究課題名 | ンプリンティング疾患の診療ガイドライン作成に向けたエビデンス 創出研究 | |
| 研究代表者名 | 緒方勤 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 浜松医科大学 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | インプリンティング疾患 | |
| 研究のフェーズ | エビデンス創出研究 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| 研究概要 | インプリンティング疾患とは、片親性発現を示すインプリンティング遺伝子の発現異常に起因する疾患である。Kagami-Ogata症候群 (KOS14)、Temple症候群 (TS14)、Silver-Russell症候群 (SRS)、Beckwith-Wiedemann症候群 (BWS)、Prader-Willi症候群 (PWS)、Angelman症候群 (AS)、新生児一過性糖尿病(TNDM)、偽性副甲状腺機能低下症(PHP)の8疾患が知られ、片親性ダイソミー、エピ変異、ゲノムコピー数異常、遺伝子内変異により発症する。本研究では、インプリンティング疾患の診療ガイドライン作成に向けたエビデンス構築を目的として、以下の項目達成に挑む。 (1) 臨床診断基準の樹立(内分泌的診断可能なTNDMとPHPを除く):既にわれわれが遺伝学的診断を行った膨大な患者から臨床情報データシートを用いて表現型を収集し、各臨床症状の性質(特異的・特徴的・非特異的)や頻度を解析する。そして、先行ガイドラインがなく、われわれが世界の最先端に位置するKOS14とTS14では世界初の診断基準を作成し、SRS、BWS、PWS、ASでは既報の国際診断基準が本邦で使用できるか否かを検討する。 (2) 遺伝学的診断システムの構築:インプリンティングセンターとして機能するDMR(メチル化可変領域)のメチル化解析とコピー数解析、ならびに各インプリンティング遺伝子のコピー数解析を同時に行えるMS-MLPA法の第1選択解析法としての位置づけ(国立成育医療研究センター研究所から導出予定)ならびに網羅的遺伝子変異解析を可能とする遺伝子パネル検査の樹立(かずさDNA研究所から導出予定)を図る。これにより、全インプリンティング疾患の正確かつ効率的な遺伝学的診断法を確立する。 (3) エピ変異発症機序の解明:受精後の異常とされてきた低メチル化エピ変異が、多座位メチル化異常という現象を伴う患者の解析からDMRメチル化維持タンパク複合体コード遺伝子の変異で生じうることが判明してきた。本研究では、低メチル化エピ変異患者において、全エクソーム解析で上記遺伝子の変異解析を行い、変異が同定されたときにはメチローム解析でメチル化異常の範囲と程度を明らかとする。これにより、遺伝性のあるエピ変異の存在およびメチル化異常の表現型への影響を明らかとする。 | |
| レジストリ情報 | ||
| レジストリ名 | インプリンティング疾患レジストリ | |
| 対象疾患/指定難病告示番号 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群(Kagami-Ogata症候群)/193、Prader-Willi症候群/201、Angelman症候群/236、偽性副甲状腺機能低下症) | |
| 目標症例数 | 5000 例 | |
| 登録済み症例数 | 2200 例 | |
| 研究実施期間 | 2022年4月~2026年3月 | |
| 関連学会との連携の有無 | あり | |
| 学会名 | 日本小児内分泌学会、日本小児遺伝学会、日本人類遺伝学会 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| レジストリの目的 | 自然歴調査;患者数や患者分布の把握;疫学研究;遺伝子解析研究 | |
| レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
| 臨床情報の調査項目 | ||
| 調査項目 | ||
| 第三者機関からの二次利用申請可否 | ||
| レジストリの企業利用について | ||
| 二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
| レジストリURL | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| 生体試料の種類 | DNA;RNA;細胞 | |
| 生体試料の登録例数 | 2000 | |
| 外部からの使用申請の受け入れ可否 | 使用目的によります | |
| 外部からの使用申請への対応 | 使用目的によります | |
| 担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。