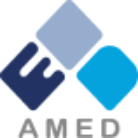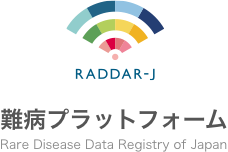| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
| 研究課題名 | プリオン病国際医師主導治験獲得のためのプリオン病早期診断基準の作成と非侵襲性診断法の開発 | |
| 研究代表者名 | 佐藤克也 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 長崎大学 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | プリオン病 | |
| 研究のフェーズ | エビデンス創出研究 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | あり | |
| 研究概要 | プリオン病では発症から3ヶ月程度で急速に悪化し無動無言に至るために、発症後超早期での迅速な診断が必須である。また現在効果が示唆されている治療薬や予防薬を超早期から投与することによる十分な効果も期待される。つまり、現在有効な治療法がない中で、ここ3年間で国際医師主導治験が始まる予定であり、早期診断基準の確立が必要とされている。これまでの研究班(水澤班及び山田班)での長年の研究により、プリオン病の補助診断法としてMRI拡散強調画像と髄液バイオマーカー検査の有用性が明らかになった。さらに我々が開発した微量の異常プリオン蛋白を増幅検出するRT-QUIC法も、特異度が非常に高い。そのためバイオマーカーに比重をおいた新規診断基準を作成した。しかしプリオン病の超早期および早期の診断基準では臨床症状よりもバイオマーカーの基準に依存しやすい。しかしながら髄液中の総タウ蛋白の上昇などのバイオマーカーは孤発性CJDの診断の参考になる一方で、バイオマーカーによっては、診断におけるプロセスを混乱させるという報告もある。 「プリオン病の早期診断・早期治療」を実現するにはこれらの問題を解決しなければならない。 又国内のプリオン病新規発症者は年間200人程度だが、孤発性プリオン病は誰もが罹りうる極めて悲惨な致死性疾患であり、家族および医療機関の負担も非常に大きい。さらに手術器具の不適切な滅菌によるヒトーヒト感染の危険性が懸念されており、高齢者が増加すると院内感染事故の危険性が高まると考えられる。実際、インシデント委員会には術後にプリオン病を発症したケースの相談が複数寄せられている。 「プリオン病の早期診断・早期治療」を実現するにはプリオン病早期診断基準を作成しなければいけない。現行の診断基準で最も問題なのは臨床症状だけでなく、髄液及び画像などのバイオマーカーが入っているが十分ではない。本調査研究では、1)新規診断基準の有効性の検証 2)早期診断基準の作成のためのエビデンス創出、具体的には臨床症状・脳波・画像(MRI検査・脳血流シンチ)・髄液検査をベースとしたバイオマーカーの検討、特に鑑別に趣を置き、早期診断のためのエビデンス構築を作成する。しかしながらヨーロッパでは2世代QUIC法による測定が重要であり、この方法以外は認めないという意見もあり、2世代QUIC法の開発と確立も行う。 上記2つで新たな診断基準策定に必要なエビデンス構築を行い、政策研究班である「プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究」班のほか、難治性疾患克服研究事業である「プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する研究」班等と強い連携を行い、2021年作成予定の診療ガイドラインの作成委員会及び会議で早期診断基準の作成を行う。 なお、併せて生体材料を採取し非侵襲性組織から診断法を開発し超早期の段階からのサンプルを利用し早期診断基準の有効性を検証することを本研究の目的とする。 | |
| レジストリ情報 | ||
| レジストリ名 | プリオン病を含む急速進行性認知症のバイオマーカー研究 | |
| 対象疾患/指定難病告示番号 | ||
| 目標症例数 | 500 例 | |
| 登録済み症例数 | 450 例 | |
| 研究実施期間 | 2023年4月~2026年3月 | |
| 関連学会との連携の有無 | あり | |
| 学会名 | 神経学会、神経感染症学会 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | あり | |
| レジストリの目的 | 自然歴調査;患者数や患者分布の把握;疫学研究;バイオマーカーの探索 | |
| レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
| 臨床情報の調査項目 |
| |
| 調査項目 | ||
| 第三者機関からの二次利用申請可否 | 可 | |
| レジストリの企業利用について | 企業が利用することについて患者の同意を取得済み | |
| 二次利用申請を受けた場合の対応方法 | 可、運営委員会で協議後、倫理委員会の承認を得て提供 | |
| レジストリURL | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| 生体試料の種類 | 血漿・血清;髄液 | |
| 生体試料の登録例数 | 500 | |
| 外部からの使用申請の受け入れ可否 | 可 | |
| 外部からの使用申請への対応 | 可 | |
| 担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。