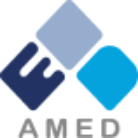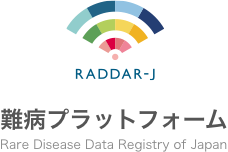| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
| 研究課題名 | ヒポキサンチン濃度をバイオマーカーとしたパーキンソン病治療薬(フェブキソスタットとイノシンの配合薬)の開発を目指した研究 | |
| 研究代表者名 | 渡辺宏久 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 藤田医科大学医学部脳神経内科学 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | パーキンソン病 | |
| 研究のフェーズ | 治験 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| 研究概要 | パーキンソン病(PD)とアルツハイマー病(AD)は重大な神経変性疾患である。PDには症状改善薬はあるが疾患修飾薬は無い。研究開発代表者渡辺宏久は26名のPD患者にフェブキソスタットとイノシンを2か月併用した臨床試験を探索的に行いPDに対する効果と安全性を示した。フェブキソスタットはキサンチン酸化還元酵素阻害薬(XORI)の一つでイノシンと協力して血液中のヒポキサンチン(Hx)を上昇させ、脳内のATPを増強するとの仮説に基づく。我々はPDではHxが低値で、更に低値の患者ほど本治療法による治療効果が強い事を見出し、血液中Hxがバイオマーカーとなる事を知財化した。本治療法に関する元々の仮説は、研究開発分担者鎌谷直之がミトコンドリア機能低下によるATP低下がAD、PDの諸障害を説明する事をヒトゲノムや進化研究などから立てた。それに対し、XORIがHx増加を介したATP増強を起こすことを見出し、更にイノシンの併用によるXORIの効果増強と副作用の低減を臨床試験で示した。最近になり米・独・台・韓の研究者が自国の保険データなどの大規模なビッグデータを解析し、様々な既存薬の中でXORIであるアロプリノールとフェブキソスタットがADを含む認知症に対して最も抑制効果があるとする注目すべき報告をした。更にXORIのPDに対する抑制効果も臨床ビッグデータで示され、我々の仮説が証明された。XORIとイノシンの併用はPDの発症のプロセスを抑制することから疾患修飾作用が期待できる。更にイノシンとXORIの投与は同時に行わないと尿酸値上昇、下降等の障害をもたらすため、ノンコンプライアンス防止のためフェブキソスタットとイノシンの配合薬の開発を目指すこととし、PD患者を対象としたPhase Ib試験の計画を建てた。今回は本事業に応募しPMDAとの対面助言を行い、医師主導治験の体制を整備する。準備が整った後に、医師主導治験により24例のPD患者に対しXORIとイノシンの至適配合比率を定め、Hxをバイオマーカーとした臨床POCを得るためのPhase Ib試験を行う。その結果をもとに、次相の治験を計画し、資金を得てそれを実施することにより本配合剤の承認を目指す。本研究でPDに対する効果が示せればADに対する効果も期待でき、神経変性疾患に悩む世界の患者さんの幸福に貢献し、社会負担を軽減することにも繋がる。 | |
| レジストリ情報 | ||
| レジストリ名 | ふじた神経疾患レジストリ | |
| 対象疾患/指定難病告示番号 | パーキンソン病/6 | |
| 目標症例数 | 180 例 | |
| 登録済み症例数 | 180 例 | |
| 研究実施期間 | 2021年5月〜2025年3月、2025年5月〜2027年3月 | |
| 関連学会との連携の有無 | なし | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| レジストリの目的 | 治験またはその他の介入研究へのリクルート;治験対照群としての活用;試料採取;バイオマーカーの探索;遺伝子解析研究 | |
| レジストリ保有者のPMDA面談経験の有無 | なし | |
| 臨床情報の調査項目 |
| |
| 調査項目 | ||
| 第三者機関からの二次利用申請可否 | 今後、検討していく予定である。 | |
| レジストリの企業利用について | 企業が利用することについて患者の同意を取得済み | |
| 二次利用申請を受けた場合の対応方法 | ||
| レジストリURL | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| 生体試料の種類 | 血漿・血清;DNA;組織;髄液 | |
| 生体試料の登録例数 | 1800 | |
| 外部からの使用申請の受け入れ可否 | 別途対応 | |
| 外部からの使用申請への対応 | ||
| 担当者連絡先 | ||
| 藤田医科大学医学部脳神経内科学 渡辺宏久 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。