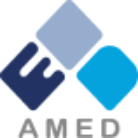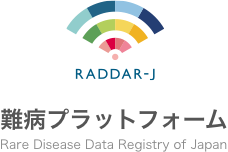| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
| 研究課題名 | パーキンソン病に対する三種酵素の遺伝子治療開発 | |
| 研究代表者名 | 村松慎一 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 自治医科大学 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | パーキンソン病 | |
| 研究のフェーズ | 治験 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| 研究概要 | パーキンソン病に対して、アデノ随伴ウイルス(adeno-associated virus: AAV)ベクターを応用してドパミン合成に必要な三種類の酵素遺伝子を被殻に導入する遺伝子治療の医師主導治験を実施する。パーキンソン病における主要な病理変化は、中脳の黒質緻密部から線条体(被殻と尾状核)に投射するドパミン産生細胞の変性脱落であり、被殻におけるドパミンの欠乏が動作緩慢、筋強剛(固縮)、静止時振戦などの運動障害の発現と密接に関連している。病初期にはドパミンの前駆物質であるレボドパ(Ldopa)の内服が著効するが、進行すると効果の持続が短くなるウエアリングオフや突然効果が切れるオンオフ現象が出現する。また、レボドパの服用後に不随意運動(ジスキネジア)を生じるようになる。ドパミンの生合成は、アミノ酸のチロシンがチロシン水酸化酵素(tyrosine hydroxylase: TH)によりレボドパとなり、続いて芳香族アミノ酸脱炭酸酵素(aromatic L-amino acid decarboxylase:AADC)が働いてドパミンに変換される。THには補酵素としてテトラヒドロビオプテリンが必要でその合成にはグアノシン三リン酸サイクロヒドロレースI(guanosine triphosphate cyclohydrolase I:GCH)が律速酵素となる。被殻においてこれらの酵素の活性の大部分は黒質緻密部のドパミン産生神経細胞からの軸 索終末に存在しており、パーキンソン病ではこの軸索終末の変性脱落に伴い活性は著しく低下している。そこで、発症後長期を経ても脱落を免れている被殻の神経細胞にこれら三種類の酵素の遺伝子を導入し、ドパミン当初より開発してきたTH、GCH、ADCの三種類の酵素をそれぞれ発現するAAVベクターを被殻に導入する遺伝子治療の治験を計画した。この方法ではレボドパの内服は不要となり、被殻内で持続的にドパミンが産生されるのでウエアリングオフやオンオフ現象を回避できる。三種類のベクターを混合し、定位脳手術により両側の被殻に注入する。安全性とともに24週後の運動機能の改善効果をMDS-UPDRS、症状日誌などにより評価する。 | |
| レジストリ情報 | ||
| なし | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| なし | ||
| 担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。