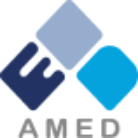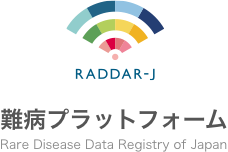| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 事業名 | 難治性疾患実用化研究事業 | |
| 研究課題名 | トリプレットリピート病の異常伸長リピート短縮による根源的治療開発 | |
| 研究代表者名 | 中森雅之 | |
| 研究代表者の所属機関名 | 山口大学 | |
| 研究対象疾患名(または疾患領域) | トリプレットリピート病 | |
| 研究のフェーズ | シーズ探索研究 | |
| 難病プラットフォームとの連携の有無 | なし | |
| 研究概要 | トリプレットリピート病とは、3塩基繰り返し配列(リピート)の異常伸長により引き起こされる疾患の総称で、CAGリピートによるハンチントン病(HD)や脊髄小脳失調症(SCA)、CTGリピートによる筋強直性ジストロフィー1型(DM1)などがある。これら疾患は、いずれもが根本的治療法のない進行性の難病であり、異常伸長リピートから生じるmRNAや蛋白が障害を引き起こす。これまでトリプレットリピート病では、異常mRNAや蛋白をターゲットとする治療研究がすすめられてきたが、いまだ十分な効果は得られておらず、根源的治療法の開発が急務といえる。トリプレットリピート病の特徴として、リピート長が長いほど、重症となる傾向がある。また、これら疾患の多くではリピート長が一定ではなく、同一患者内でもリピートは年齢とともに伸長して症状の進行に寄与する。逆の見方をすれば、異常伸長したリピートを短縮することが可能となれば、症状の改善や発症予防が期待できる。 申請者らは異常伸長CAGリピートDNAに特異的に結合する核酸標的低分子ナフチリジンアザキノロン(NA)にDNA修復機構を調整して異常伸長リピートを短縮する作用があることを発見し、HDモデル動物、SCAモデル動物でその効果を実証している(Nature Genetics, 2020)。NAは、異常伸長CAGリピートへの結合性が非常に高く、HDマウス脳組織において1か月間で5リピートの短縮が達成されており、HD患者へ外挿すると2年間の治療で異常伸長リピートを正常化できることが期待されるが、生体内での安定性が低く、実用化への障壁となっている。本研究では、トリプレットリピート病の伸長リピート短縮治療実用化を進めるため、NAを元に構造展開を行い、より安定性が高く、生体内でより強い薬効をもつ核酸標的低分子を創成する。また、NAの鼻腔内投与で脳内への移行も確認しており、HDやDM1での標的組織移行性を高める投与経路の最適化も行う。核酸標的低分子によりリピートの短縮が可能となれば、生成される異常蛋白の負荷が軽減されて症状の改善が期待できるほか、早期治療介入による進行抑止や未発症保因者の発症予防も可能となる。異常伸長リピートを短縮誘導して正常化する、これまで試みられたことのない革新的アプローチで、トリプレットリピート病の根本的治療法開発を目指す。 | |
| レジストリ情報 | ||
| なし | ||
| バイオレポジトリ情報 | ||
| なし | ||
| 担当者連絡先 | ||
※メールアドレスが掲載されている場合は、「●」を「@」に置き換えてください。